|
|
メダカは、産卵する・・・・・当たり前であるが、考えてしまう。
卵が全部、孵化してしまったらどうしよう、育てきれない。 などと思い込んでいても、
実際問題として、無精卵があり、発生途中で生きるのを止めてしまう、中止卵がある。そしてカビてしまう卵。
その卵に巻き込まれて、カビを頂いてしまい、あえなくリタイヤ・・・・・という羽目に陥るものもある。
カビの塊で、あきらめていた中から、1、2匹孵化してきた喜びもつかの間、育たなかった・・・・・。など、
次から次へと、問題が起きてくる。
メダカの雌雄の見分け方や、飼育方法も解らずに、試行錯誤の連続で、
ガッカリするやら、ニヤニヤするやら、時にはメダカ達に驚かせられる。
そんなこんなで、時間がたった。デモまだ数年。
♪メダカの学校♪ のイメージで、メダカはみんな、仲良しだとの認識があったが、
オス同士の縄張り争いがあるのにビックリした。観察していると、孵化してまだ1週間ほどなのに、
もう生意気に、クルクルとオス特有の回転運動をしている稚魚もいる。
メスはメスで、なかなか卵を産まないで、水槽の底に座り込んで動かない。
隅の方で、ガラスの壁面にピッタリと背中を付けて、まったく動こうとしないメスまでいる。
どうやら、体の周りや、目の前で、回転運動をされると、動けなくなってしまうようで、
卵を産みたくない時や、嫌いなオスをやり過ごそうとメスも、色々考えているようだ。
そうかと思えば、あっさりと産卵するメスがいる。

======================================================================================***★☆★
採卵のしかたも、色々試したが今は、卵をお腹にぶら下げているメスを網ですくい、
網の外から卵を指でつまんで採っている。
網の中では、卵が全部採卵できたか、残っているのか判別できないので、
水中に網をつけて、メスが網から出ないように注意しながら、お腹を見て、
卵がまだメスのお腹についているなら、再度指でつまんで採る。
メダカの卵は、受精直後だと硬くて、ちょっとや、そっとじゃ潰れない。
そこで、スポンジフィルターを使い、水槽の底を擦って、卵を付着させて、それを指で摘んで採る。
付着しない卵もあるので、残っているものは、最後にスポイトで、吸い取っている。
運悪く、孵化直前の卵が潰れてしまう事もある。しかし、親に食べられる事を思えばこれ位は、良しとする。
水槽に余裕があるときは、卵を水槽に入れておくが、場所がないときは、食パンのケースや、
プラケース、時にはプリンの小さいカップに入れておく。
昨年、寒くなり、ヒーターを出すのが面倒だったので、蓋付きのプリンカップに、採卵した卵を親別に番号を振り、
日付を書き込んで、発泡スチロールの箱の中に入れた。
ペットボトルに25〜28℃の、お湯を入れて湯たんぽ代りに使用。
プリンカップに直接、ペットボトルが触れないようにして置いて、温度計を入れた。
翌日の朝、卵と水温をチェックしながら、孵化した子は、少し大きめのカップに移し、
餌を食べだした子には、パウダー状の餌を指につけて払い落としてから、落とした後の指を擦り合わせて、
かすかに餌が浮いているのを確認したあと、蓋をして置いた。
余裕のあるときは、カップを2段重ねにし、上には卵や稚魚たち。下は汲み置きの水。次の日、
チェックがてら汲み置き水に、1滴ずつ液体の塩素中和剤を入れ、そこに卵と稚魚たちを毎日移していた。
(今考えると、やり過ぎかも知れません?2・3日に1回くらいがいいかな?)
白い発泡スチロールの箱は、蓋をしても結構光を通すようで、明るい。
最初はたびたび箱を開けて、温度のチェックをしたが、心配するほど温度は下がっていなかった。
ホッカイロなどは、空気に触れないと、発熱しないので、箱に空気の通過する穴を開けなければいけない。
ちょうど好いお手頃サイズの発泡スチロールの箱は、貴重で穴を開けたくない。
そこで考えた、苦肉の策のペットボトル湯たんぽは、お手軽で、なかなか具合が良かった。
1cm前後に成長した頃、ヒーターの入っている兄弟たちの水槽に放していた。
それでも、2cm過ぎまで育ってくれるのは少なく、飼い始めた頃は、何故だろう???と思いつく限りの事を試してみた。
======================================================================================***★☆★
熱帯魚のグッピ−は、産まれるとほとんどが育つ。卵胎生なのに子供じゃなく、まれに卵を
産むことがあったのを思い出した。グッピーは、産まれる前にお腹の中で育たない子供が消えてしまい、
元気な子供だけが、産まれてくるとしたら?
メダカの卵は全部、孵化すると思い込んでいた。しかし卵の中で、そして産まれてからも、
育たない子供がいるのでは、ないのだろうかと考えてみた。

熱帯魚のショーベタでは、卵の中に目があるにもかかわらず、孵化しない。
産まれても育たない個体が存在する。特に、ブラックのベタは、非常に繁殖が難しい。
色によって繁殖の難易度が違うのである。他にも原因はあるが、一因なのは確かである。
そう考えると、なんとなく納得。。。。
色々メダカのサイトを検索してみると、メダカには、思ったより多くの致死遺伝子が存在すると解り、
自分の飼育のまずさではないのだと、安心する。それにしても、きれいな体型の成魚になる、
光メダカ達のなんと少ない事か?2cm過ぎてからも、体型が崩れてしまう個体が多い。
これは、変わりメダカの飼育人口が少なく、メダカの個体数が絶対的に足りない。その要因がある上に、
成魚になるまでの時間がかかる。人件費、維持費などのコストがかかってしまい、
メダカを安価で販売できないのが最大の原因ではないかと考えている。
安価で販売できるのは、最も狂いの少ない、2cm前後である。そうすると、購入してから、
育たないものや、いろいろな障害が出てくる。それでも、卵を産んでくれると良いが、
次の世代が取れないのは、ガッカリしてしまう。
光メダカの成魚は、4cmはオーバ−する。
メスなど、その色の特徴がはっきり解って、それはきれいで、思わず魅入ってしまうほどである。
グッピ−のような派手さはないが、日本の、わびさびの世界そのもので、
日本人なら理解できるであろう上品な、魚たちであると考えている。
メダカは、難しい・・・奇形の多いのが、現時点では当たり前なのかもしれない。
フルサイズの成魚になってから、長い間健康な体型でいられるメスは、皆無に等しい。
それに比べてオスは長い間、きれいな姿勢を保て、長生きして孫娘と子孫を残すことをやってのける、兵ぞろいである。
産卵が、命を縮めてしまう、大変な重労働なのだと、つくづく思う。
======================================================================================***★☆★
変わりメダカの飼育人口が、増えると安く供給できる。そうすると、丈夫なメダカが増えてくる。
良い事尽くめダケではないだろうが・・・・・。今より少しは、元気なメダカ達が増えてくれるといい。
しかし、やはり良い個体は、ごく少数しか産まれないだろう。
金魚の王様といわれる、らんちゅうなどが、良い例ではないか?大量生産の、安価ならんちゅうは、
100円単位で発売されているが、有名どころの血筋になると、天井知らずの値がついていると伝え聞いている。
そのうちメダカも、ブランド物、大衆物などと分かれて行くのかもしれない。
非常に悩んでいたものに、メダカの体色であった。なにがどうで、どうなって??さっぱり解らなかったが、
思い切って≪メダカ学全書≫を購入した。それで、やっとのことで、色がわかった。
無色のために、体の血液が透けて見え、薄いクリームやピンク色に見える。
濃白色で、体にシュガーパウダーをふりかけたように、不透明な白色で、尾びれは黄色。
濃白色で、体にシュガーパウダーをふりかけたように、不透明な白色で、尾びれは白色。 また、参考に、同型接合体という遺伝子記号を書き出してみました。 茶色=BBRR オレンジ=bbRR 青=BBrr 白=bbrr |
カルチャーショックを受けたもの・・・・・・何をどう、表現したらよいのか?困ってしまった事。
商業的なものと違っていた。メダカの体色。
ただ、知ったからといって、見た目には、あまり大差がないが、遺伝的には、大いに大差の在るものである、
と言うことを認識していただければと願っています。
【い】茶色=BBRR++ ・・・・・・茶色で、尾は濃い黄色 【ろ】灰色=BBRRcici ・・・・・・見た目、青色で、尾が黄色 【は】オレンジ=bbRR++・・・・・オレンジ色、尾は濃い黄色 【に】クリーム=bbRRcici ・・・・・見た目、白(ミルキー )で、尾が黄色 【ほ】青色=BBrr++ ・・・・・・・・青色で、尾は白色 【へ】うすあお色=BBrrcici ・・・・見た目、淡青色で、尾が白色≪淡青色≫ 【と】白色=bbrr++ ・・・・・・・・・薄いクリーム、又はピンクで、尾が透明 【ち】白色=bbrrcici ・・・・・・・・・見た目、濃い白で、尾は白色≪ミルキー≫ |
青色と言われている中には、【ろ】【ほ】【へ】が、市販されています。
白色と言われている中には、【に】【と】【ち】が、市販されています。
ciciという、白色が濃くなる遺伝をもっていると、本来の色が隠れて、別の色に見えてしまうという、
目くらましが、メダカの厄介さに、ますます拍車をかけています。
おまけに、オスにはあって、メスにはないと言う、性染色体上の遺伝まであります。
ちなみに、++というのは、野生型で、白い色が、ごく少数しかないようです。
もひとつおまけで、不完全優性という代物まで、存在しているようです。
またまた、おまけがついて、大サービスで、メダカ達の色は、こんなに単純では、ないようです。
一番賢いのは、ほどほどに基本を踏まえて、メダカ達をよく観察して、飼育する事が、
成功の近道では無いかと考えています。
グッピーで、理論を踏まえて、書き出してみたらうんざりしてしまった事があります。
何十通りの組み合わせならまだしも、色々な確率を考えていると、やっていられない世界に落ち込んでしまいます。
観賞魚雑誌に、書いてあるのは、実は、私のやっていた事柄の、ほんのさわりだけなのです。
下手の考え休むに似たり・・・・・って諺がありますが、まさしく其の通り。
考えるより、実行。・・・・・CMの・・・・・あったまダケでも♪かっらだダケでも♪だめよね♪・・・・・・
という、まさしくそのものズバリですよね。
交配表に載っていないのは、自分のほしい品種に、置き換えて考えてみてください。
基本は変わらないのです。
また同時進行させるという手もありますよ。ペアをバラバラにして、片方はアルビノ作出に使い。
もう片方は色の作出をして、出来たものをあわせて、孫で出す。
好きなタイプのメダカを作出するために、楽しんでやりましょうね。急がば回れ・・・ともいいますし。
======================================================================================***★☆★
今回、交配表をアップするにあたり、良識ある方には必要がないことですが、ネットに、詳しい方から忠告を頂きました。
匿名性の高い、インターネットには残念ながら、批判や中傷が多いことも事実のようです。
もしこのHPの、今回アップした交配表について、私の至らないところ等がありましても、
誹謗・中傷などは、ご遠慮お願いいたします。間違っているところ等、メールで教えて頂くのは、大歓迎です。
不満がありましたら、自分の、氏名・都道府県名などを明記し、責任を持ってHPを立ち上げて頂きたいと思います。
専業主婦で、収入が有りませんが、HPは有料サイトを使用し、皆様のご相談などを、無料で行っています。
多少は、皆様のお役に立てていると、うれしいのですが・・・そして、独学で学び、どなたからも、教えて頂いていません。
先生は、切望しています。どなたかいらっしゃいませんでしょうか?それらもお含み置きの上、ご了解をお願いいたします。
なお、誤記があっても、しばらく更新は不可能なので、お許しください。
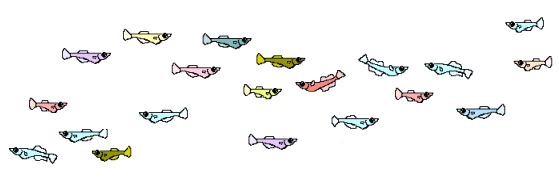
2003年11月 追記
管理人:知恵子 HP作成担当:あずま 無断転載:upa
Copyright(C)2002
chieko&azuma
All righets reserved.
since 2002.10.23